
この記事では、飲酒運転防止のための具体的な取り組みである「ハンドルキーパー運動」についてご紹介します。この運動は、飲酒運転を未然に防ぐための具体的な取り組みとして、多くの企業や個人が導入を進めています。この記事では、ハンドルキーパー運動の具体的な内容やその意義について詳しく解説し、飲酒運転防止のための実践的なアドバイスを提供します。
2025/01/31 公開
目次
ハンドルキーパーとは?その役割と意義

ハンドルキーパーとは、飲み会やイベントなどの飲酒の席で、運転を担当する人のことを指します。ハンドルキーパーの主な役割は、事前に飲酒をしないことを決め、飲酒の席でお酒を飲まず、他の参加者が安全に帰宅できるように運転を担当することです。
英語ではハンドルキーパーは「designated driver」(指名された ドライバー)と言いますが、この言葉通り、ハンドルキーパーを事前に指名しておくことがポイントです。ハンドルキーパーを決めておくことは、事故を未然に防ぐための重要な手段となります。
ハンドルキーパーが存在することで、参加者全員が安心してイベントを楽しむことができ、帰宅時の安全も確保されますね。飲酒運転による悲惨な事故を防ぐためには、ハンドルキーパーの役割を理解し、その意義を広めることが重要です。ハンドルキーパー制度は、個人の意識向上だけでなく、社会全体での交通安全の向上にも寄与します。
◾️ 「ハンドルキーパー運動」とは?その背景と実施内容
実施の背景
「ハンドルキーパー運動」は、飲酒運転を防止するための社会的な取り組みとして発足しました。この運動は、福岡県福岡市の飲酒事故等、飲酒運転による悲惨な事故が発生した背景を受けて、2006年(平成18年)に始まりました。「全日本交通安全協会」、「日本自動車連盟」、酒類提供の立場である「日本フードサービス協会」の三団体が運動を推進しています。
具体的な実施内容
「ハンドルキーパー運動」では飲酒運転の危険性を広く認識させるため、行政機関での広報活動や各地域コミュニティの安全協会によって、さまざまなキャンペーンや啓発活動が行われてきました。
ポスターやパンフレット、他アイテムを使って広く周知・啓発運動をしているため、居酒屋やカラオケボックス等で目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。(全日本交通安全協会「ハンドルキーパー運動の推進」)
このように、飲酒運転の危険性とハンドルキーパーの重要性を訴えています。
また、酒類提供を行う飲食店と連携して、飲酒運転を未然に防ぐための様々な工夫が実施されています。
- 車で来店しているかどうかの確認
- ハンドルキーパー(運転者)が決まっているかの確認
-
ハンドルキーパー(運転者)に酒類を提供しないようにする工夫
…運転者へは別のグラスで飲み物を提供する、運転者をリストバンドで目印をつける、運転者の席に目印を置く等。 - 運転代行サービスの呼び出し、運転代行サービスが到着するまでの間は車の鍵を飲食店で預かる
「ハンドルキーパー運動」の実施内容は多岐にわたりますが、「飲酒する前にハンドルキーパーを決定すること(飲酒する人と飲酒しない人を明確に分けておくこと)」がこの活動の肝です。
ではなぜ、“飲酒する前に”ハンドルキーパーを決める必要があるのでしょうか。
それには、飲酒運転のリスクと恐ろしさに理由があります。
飲酒運転のリスクと法律

飲酒運転は、運転者の判断力を著しく低下させ、重大な事故を引き起こすリスクを伴います。
法律では、飲酒運転に対して厳しい罰則が設けられており、違反者には免許停止や罰金、さらには懲役刑が科されることもあります。
- 飲酒運転の行政処分と罰則について以下の記事でもご紹介しております▼
飲酒運転撲滅のために企業の安全運転管理者が知っておくべきこと
◾️ なぜ飲酒運転はいけないの?
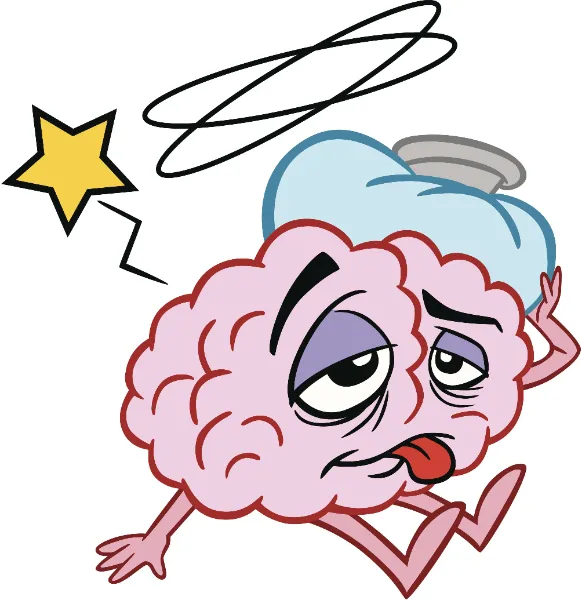
アルコールの摂取により、「中枢神経系」という脳と脊髄からなる神経系の働きを鈍らせます。脳や身体の司令塔となる中枢神経系を抑制されるため、運転中の反応を遅らせ、重要な判断を遅らせることになります。 また、視野が狭くなったり、気が大きくなったりします。人は運転している際、周囲の状況をよく見て細かい判断と身体の制御を繰り返しています。体調に問題がなく理性的でない限り、ハンドルを握ってはならないのです。
法律では、飲酒運転に対して厳しい罰則が設けられており、違反者には免許停止や罰金、さらには懲役刑が科されることもあります。
また、飲酒運転は個人の問題に留まらず、企業のイメージにも大きな影響を与えます。従業員が飲酒運転を起こした場合、その企業の社会的信用が低下し、顧客や取引先からの信頼を失う可能性があります。実際に、飲酒運転による事故が企業の評判を著しく損なった事例も多く報告されています。このようなリスクを避けるためにも、企業として飲酒運転防止に取り組むことが求められています。
◾️ 飲酒運転は同乗者にも責任あり!
ドライバーがアルコール摂取したことを知りながら見過ごすと、同乗者にも刑事責任が発生します。
| 飲酒運転の種類 | 同乗者への罰則 |
|---|---|
|
酒気帯び運転 (呼気中アルコール濃度が0.15mg/l以上の場合) |
2年以下の懲役 または 30万円以下の罰金 |
|
酒酔い運転 (アルコールの影響により正常な運転ができない状態) |
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |
(みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」|警察庁Webサイト)
また、車両の提供者や酒類の提供者にも厳しい罰則が科されます。
飲酒運転は、交通事故を引き起こし、周囲に甚大な被害を及ぼします。
悲惨な事故の原因になり得る飲酒運転は、ドライバーだけではなく、関わった人の人生を壊します。
飲酒運転根絶のためには、「ハンドルキーパー運動」が重要

繰り返しになりますが、アルコールは脳の司令塔である「中枢神経系」の動きを鈍らせ、気も大きくさせます。飲酒をしてからでは、普段どれほど理性的な人でも、正常な判断は出来なくなり、油断が生まれます。
そのため、飲酒事故を防ぐためには、飲酒の前にしっかりとした対策を講じることが重要なのです。「ハンドルキーパー運動」は飲酒運転防止のための簡単で有効手立てです。
◾️ ハンドルキーパーは「いつ」「誰が」「どうやって」決める?
-
ハンドルキーパーは、必ず飲酒前に計画的に決めましょう。
飲酒を控えることに抵抗が無い人、普段から運転に慣れている人が適任です。 -
ハンドルキーパーが決まったら、事前に参加メンバーに知らせましょう。
うっかりアルコールを渡してしまうことを防ぎ、ハンドルキーパーを配慮するためです。
ハンドルキーパーには、飲み会の送迎という負担がかかります。この負担を軽減するためには、事前にメンバーで送迎計画を立て、飲み会の費用をハンドルキーパーに割引するなどの配慮が有効です。
-
運転代行サービスの利用や、周辺の宿泊施設を事前予約するのも手!
参加メンバー全員でお酒を楽しみたいときは、運転代行サービスや宿泊施設の利用を検討しましょう。いずれにしても、飲酒前の事前の準備が肝心です。
◾️ 運転代行を利用する時の注意点!
運転代行の手配は、乾杯の前に済ませましょう。飲みすぎ防止や深夜遅くの帰宅を防ぐことができます。
ここで注意しておきたいのが、運転代行の目的地は自宅までとすることです。運転代行利用後に自宅の周辺で飲酒運転事故を起こしたり検挙されたりする事例が多いです。目的地は最寄りのコンビニの駐車場や大通りとはせず、「自宅の駐車場まで」としましょう。
社会全体で取り組む飲酒運転防止
社会全体で飲酒運転を防止するための啓発運動やキャンペーンは各所で実施されています。飲酒運転発生のリスクが高い年末年始や大型連休前、歓送迎会シーズンではより一層力を入れて活動がなされています。
各地方自治体でも、飲酒運転根絶のための都道府県条例が施行されています。(飲酒運転根絶に関する条例|一般財団法人地方自治研究機構)
地域の交通安全協会や県警を通じて、地域住民の理解を深め、飲酒運転を社会的に許容しない風潮を醸成しています。
◾️ 飲酒運転防止のための技術的なサポート
技術の進歩により、飲酒運転防止のための新たなサポートが可能になっています。 その一つがアルコール・インターロックです。これは、車両のエンジンを始動する前に、ドライバーがアルコール検査を行い、基準値を超えた場合はエンジンがかからない仕組みです。このシステムは、飲酒運転を物理的に防ぐため、特に運送業界の企業での導入が進んでいます。
さらに、スマートフォンアプリを活用した飲酒運転防止の取り組みも注目されています。これらのアプリは、飲酒量を記録し、運転の可否を判断するサポートを提供します。
◾️ 企業の飲酒運転防止は「アルコールチェック」で防ごう

企業における飲酒運転防止策として、アルコールチェックの導入が効果的です。
2022年4月1日からは、白ナンバー車両を使用する事業者においても、アルコールチェックが義務化されました。また、2023年12月からはアルコール検知器を用いてのアルコールチェックが義務化され、社会全体で飲酒運転根絶のための取り組みが強化されています。
弊社「株式会社AIoTクラウド」では、白ナンバー事業者に向けたアルコールチェックのクラウド管理サービス『スリーゼロ』を提供しています。
アルコールチェックに関する業務の負担が大きいとお困りの事業所は『スリーゼロ』の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
この記事では、飲酒運転防止のためには事前の対策と飲酒運転を起こさない仕組み作りが重要であることをお伝えしてきました。従業員の飲酒運転防止のためにはアルコールチェックが必要ですが、飲酒運転防止の企業風土を醸成し、対策の仕組みを定着させていくためには、運用の手軽さが肝になります。
『スリーゼロ』は120種類以上の検知器に対応しており、市販のアルコール検知器を使ってアルコールチェックを行えます。事業所ごとに別々のアルコール検知器を使っても、クラウド管理ができるため、導入のハードルが低く、運用しやすいのが特長です。
興味をお持ちの事業所の方は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。
