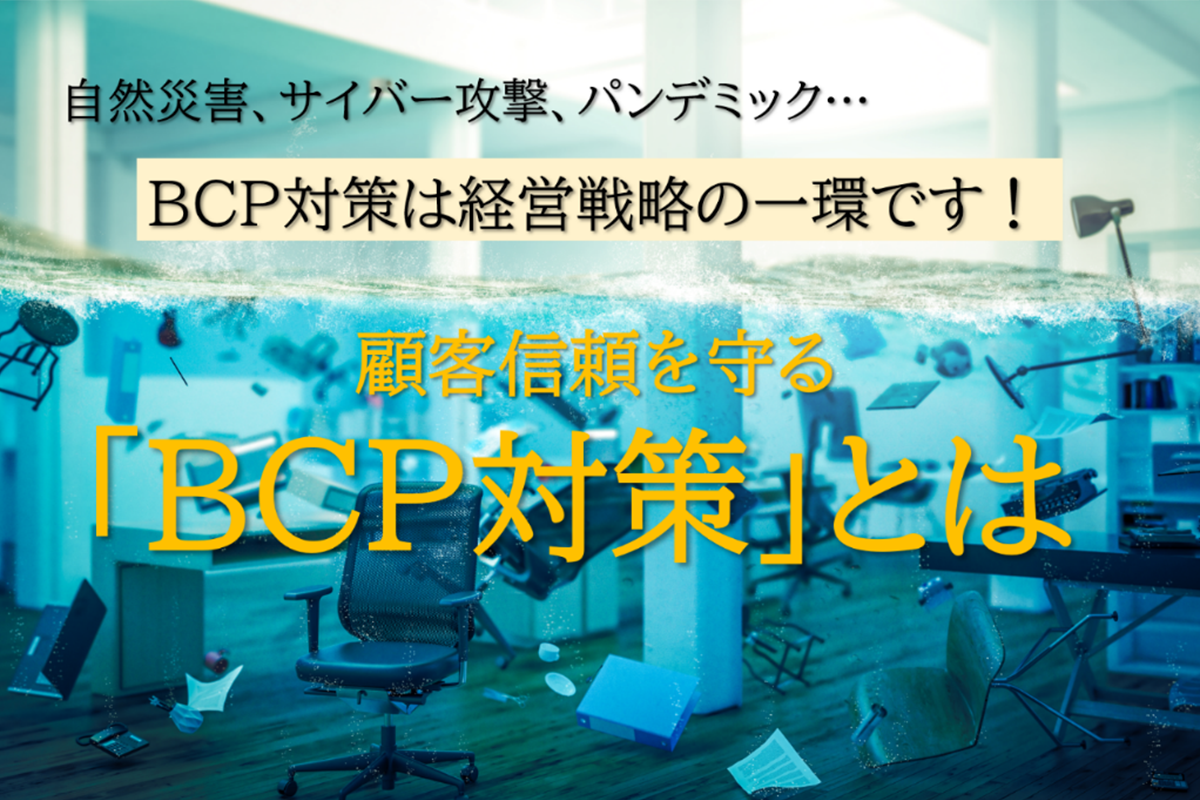
社会情勢やビジネスの急激な変化が多く、不確実性の高い現代。企業においても経営を揺るがすような予測不能な災害や危機がいつ訪れるかわかりません。そんな中、企業が事業を存続し、顧客からの信頼を維持するためには、事業継続計画(BCP)の設計と実行が必要です。本記事では、経営者じゃなくとも知っておきたいBCP対策やリスクマネジメントの基礎知識についてご紹介いたします。
2025/03/13 公開
目次
BCP対策(事業継続計画)とは?

◾️ BCP(事業継続計画)の定義と目的
BCPとは、「Business Continuity Plan(事業継続計画)」の略で、企業が災害や事故などの予測不能な非常事態が発生した際に事業を継続・早期復旧するための計画や対策のことです。(用語解説‐BCP対策とは)
BCPの目的は、業務の中断を最小限に抑え、迅速な復旧を可能にする行動計画のことです。この計画には、リスクの評価、事業中断の影響度の把握と優先順位づけ(重要業務の特定)、復旧手順の策定などが含まれます。
これにより、企業は顧客へのサービス提供を途切れさせることなく続けることができます。
BCP(事業継続計画)の定義と目的
BCP対策が求められる背景には、近年の自然災害の頻発やグローバル化によるサプライチェーンの複雑化、そして、情報技術の進化に伴うサイバー攻撃等の脅威の高まりがあります。
こうした状況下で、企業は以前にも増してリスクにさらされていますが、事業継続計画を策定することは、企業の存続に不可欠な要素となっています。
◾️ BCP対策は、経営戦略の一環である
企業が経営のリスクに備えて、リスク管理の強化や緊急対応を社内で策定することは、事業経営や従業員の安全を守ることができ、その企業の内側を守ることができます。
また、BCP対策は、企業の外に向けた経営戦略でもあります。
BCP対策を行うことで、顧客・取引先の信頼を守ることや、法規制・業界標準に準拠すること(法令遵守を徹底すること、業界のルールに従うこと)ができます。これらの取り組みは企業のブランド価値向上や企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)の寄与にもつながるのです。
以上のことから、BCP対策は、経営戦略の一環である、と言えます。
特に建設業界はBCP対策が急務である

弊社でも多数のお取引のある建設業界ですが、特に建設業界は以下2点の理由からBCP対策が急務であると言われています。
- 社会基盤、公共インフラへの影響が大きい
- 災害発生時の迅速な対応が求められる
建設業界は、道路や橋梁、建物などのインフラを維持・復旧する重要な役割を担っています。建設業界の事業がストップすると社会全体に大きな影響が及ぼされます。 また、自然災害などの非常事態が発生した際、迅速な対応が求められるのも建設業界です。災害が発生した際は、建設業界の復旧支援活動により復興してきました。
また、昨今世間で言われている建設業界のリスクは自然災害リスクだけではありません。
◾️ 建設業界はサイバー攻撃の標的になりやすい!?
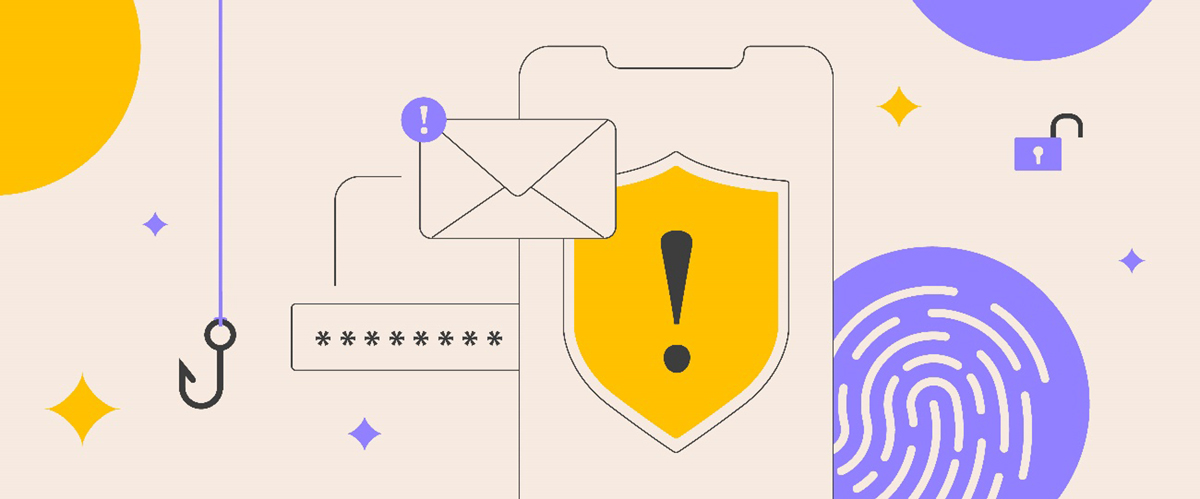
建設業界はサイバー攻撃等の「サイバーリスク」に晒されていると言われています。
以下の理由から、特に建設業界は、ランサムウェア(データを人質に取るサイバー攻撃)の標的になりやすい、と言われています。
-
建設DXの過渡期である:
建設業界では、人手不足や人材の高齢化が顕著な業界です。このことから、プロジェクト管理や建設プロセスにおいて、デジタルツールの利用が増えています。この建設業DXに伴い、サイバー攻撃のリスクも増えています。 -
中小企業が多い:
建設業界は、中小企業が多い業界です。特に中小企業では、セキュリティ対策が十分に整っていないことが多く、標的にされやすいと言われています。 -
プロジェクトの特性:
建設業界のプロジェクトは、社会への影響が大きく、その分プロジェクトに投資する金額が大きく、工期が長いです。
サイバー攻撃によるシステムの停止が大きな影響を及ぼすため、攻撃者は多額の身代金を人質に建設業を標的にすると言われています。
以上の理由から、建設業界はサイバーリスクの面に関してもBCP対策を行うことが急務であると言われています。
BCP対策は、企業経営のリスク管理「クライシスマネジメント」から始めよう!

この章では、BCP対策を具体的に策定する際に知っておきたい、「クライシスマネジメント」の基本概念についてご紹介いたします。
◾️ クライシスマネジメント(危機管理)とは。BCPとの違い
クライシスマネジメント(Crisis Management) とは、企業が自然災害やサイバー攻撃、事故などの危機(クライシス) に直面した際に、その影響を最小限に抑え、迅速に対応・復旧するための管理プロセスです。
BCPは、企業が自然災害やサイバー攻撃などの緊急事態に直面した際に、事業を継続または早期に復旧するための計画を事前に策定するものである一方で、クライシスマネジメントは、予測できない危機的状況が発生した際の初期対応や、被害を最小限に抑えるための事後の活動を指します。
企業はクライシスマネジメントとBCPの両方を取り入れることで、予測可能なリスクと予測不可能な危機のどちらにも対応できるようになります。
そのため、BCP対策を考える際は、まずは普段からクライシスマネジメントのステップを踏んでおくことが大切です。
▼クライシスマネジメント 5つのステップ
-
リスク評価:
潜在的な危機(リスク)を特定し、その影響範囲と影響の大きさを評価します。 -
危機対応計画の策定:
危機発生時の対応計画を作成します。緊急連絡のフロー作成や情報発信のルール策定、広報戦略等も含まれます。 -
モニタリング:
1.で特定したリスクをモニタリングし、危機の兆候を見逃さないようにします。 -
危機発生時の対応:
危機が発生した際は、②で策定した計画に則り、迅速に対応します。 -
振り返り:
危機が収束し、事業復旧後、④の対応の評価を行い、改善を計画し、次に備えます。
◾️ 効果的なクライシスマネジメントを実現するポイント
クライシスマネジメントを実現するためのファーストステップとして、リスクの特定と評価が重要ですが、企業経営におけるリスクとはどのようなものがあるのか、洗い出してみましょう。
ここでは一例として、以下の表にまとめてみました。
| リスクの種類 | 主な事例 |
|---|---|
|
自然災害のリスク 大地震や甚大な被害をもたらす台風等。 |
|
|
サイバーリスク ITシステムやデータの脅威のこと |
|
|
レピュテーションリスク 風評リスクのこと |
|
| 政治リスク・地政学リスク |
|
| 人的リスク |
|
| 法務リスク |
|
このほかにも、企業のおかれた環境や事業形態によって様々なリスクが挙げられることでしょう。企業経営のリスクにつながるきっかけは、実は私たちの身近にあることが分かります。
企業は、潜在的な危機を予測し、それに対する備えを整える必要があります。また、明確な指揮命令系統の確立も欠かせません。これにより、危機発生時に迅速な意思決定が可能となります。さらに、定期的な訓練と見直しを行うことで、実際の状況に即した柔軟な対応が可能となり、企業の危機対応能力を向上させることができます。
具体的なBCP対策の構築方法
この章では、BCP対策の具体的な構築ステップをご紹介します。
リスクマネジメントのうち、クライシスマネジメントがリスク全体を包括した対応計画であるのに対し、BCPは緊急事態に直面した際の事業継続と早期復旧に特化したものです。
▼BCP対策構築のステップ
-
リスク評価:
事業に影響を与える可能性のあるリスクを特定し、その影響度を評価します。
事業を軸に判断・評価するのがポイントです。 -
重要業務の特定:
業務の優先順位をつけ、重要業務を特定します。 -
対策の策定:
リスクに対する具体的な対策や手順を策定します。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。- 事業の復旧手順の策定
- 業務の代替手段の確立、確保
- ステークホルダ(従業員、顧客、取引先、関係会社など)に対してのコミュニケーション計画策定
-
資源の確保:
事業経営に必要な資源を確保し、非常時に事業が滞らないように準備します。
★例えば?
- 施設・設備の資源確保のために、サテライトオフィスの設置やテレワーク環境の整備
- データの確保のために、データバックアップの仕組み作り
- サプライチェーンの確保のために、生産拠点の分散や非常時の生産体制を構築、供給が滞らないための物流を確保
-
具体化と訓練:
万が一の際に計画が実行できるように計画を具体化させ、訓練を行いましょう。
具体的な準備や関係者への教育には時間がかかります。 -
モニタリングとレビュー:
計画の有効性を定期的に確認し、必要に応じて改善します。
◾️ 業界別に見るBCP対策の実例
各業界でのBCP対策は、その業種特有のリスクに対応するために異なるアプローチが取られています。例えば・・・
製造業では
生産が中断されるリスクを最小限に抑える傾向にあります。
サプライチェーンの断絶に備えた代替供給ルートの確保が重要視されます。
金融業では
サイバーセキュリティの強化やデータバックアップ体制の構築が不可欠です。
医療業界では
パンデミック時の医療資源の確保や、緊急時の患者対応体制の整備が求められます。

以上のように、各業界が直面するリスクに応じた具体的な対策の導入を考えなければなりません。
BCP対策を策定する場合は、内閣府や中小企業庁から出されている「ガイドライン」を参考にするのがオススメです。
▼参考記事
- 内閣府 「事業継続計画策定ガイドライン」
- 中小企業庁 「中小企業BCP策定運用指針」
◾️ 車両・ドライバーにかかわるリスクマネジメント
トラックやタクシーなどの緑ナンバー車両に限らず、社用車を使用する機会がある事業者は、車両・ドライバーに対するリスクマネジメントも重要です。
例えば、
-
アルコールチェック管理サービスの導入&運用管理
業務中の従業員が飲酒運転におよび、その結果交通事故を起こしたとなれば、企業に対する影響は避けられず、SNSなどの拡散によって、取り返しのつかない事態になることも否定できません。
飲酒運転を行なった本人だけでなく、会社に対しても刑事・民事責任だけでなく、車両使用停止、事業停止、営業許可取り消し処分等の行政処分が科されることもあります。そのためにも、企業として飲酒運転を起こさせない環境づくりは重要です。 -
車両管理システムの導入
車両位置をリアルタイムで把握できる車両管理システムを導入していれば、いざという時でであっても、素早く正確に位置や安否の状況を確認できるようになります。自然災害発生時は道路の損傷や渋滞により、身動きが取れなくケースも少なくありません。
車両管理システム導入によって、車両・従業員の所在確認などいざという時に有効な手段となります。 -
PHV・HV車など家庭用電源ソケットを装備している車両の導入
電気自動車は給電システムとしても使えるため、導入しておくことで、緊急時における充電や明かりの確保確保などにも有効です -
緊急時の行動指針の策定
有事の際に、社員が焦らずに適切に行動できるように、緊急事態発生時における対応や、機器の使用方法、会社への連絡先の徹底など、定期的に社内教育・徹底することも重要です。
まとめ:顧客信頼を守るためのBCP対策の必要性
BCP(事業継続計画)は、リスクマネジメントの一環で、企業が予期せぬ事態に直面した際にも業務を継続できるようにするための重要な戦略です。また、「クライシスマネジメント」の
BCP対策を適切に設計し、実行することで、企業は緊急時にも迅速に対応し、顧客の期待を裏切らないばかりか、信頼獲得・ブランド価値向上の機会であることが分かりました。
特に現代のビジネス環境では、自然災害やサイバー攻撃などのリスクが増大しており、企業はこうしたリスクに対する耐性を高め備えておくことで、有事の際に信頼性の高いパートナーとして顧客からの信頼を確立することができます。結果として、BCP対策は企業の競争力を向上させ、持続可能な成長を支える重要な要素であり、大事な経営戦略の一環です。
◾️ 企業のリスクマネジメントの第一歩に、アルコールチェックのクラウド管理『スリーゼロ』を導入しませんか?
弊社AIoTクラウドでは、企業の飲酒運転の根絶やガバナンス向上のため、白ナンバー事業者向けのアルコールチェックのクラウド管理サービス『スリーゼロ』を提供しています。
日々のアルコールチェック業務に対して、「しっかり運用出来ているか分からない」と不安を感じている管理者、業務負担改善をお考えの管理者は、ぜひお気軽にお問合せください。
アルコールチェック管理は、企業のリスクマネジメントの一環です。企業の信頼性を高め、万が一に備えた体制づくりが、企業の持続的な成長につながります。
まずはリスクマネジメントの第一歩に、『スリーゼロ』を導入してみませんか?
1分で簡単ダウンロード(無料)
『スリーゼロ』
紹介資料ダウンロード
アルコールチェック管理サービス
『スリーゼロ』のお問い合わせはこちら
